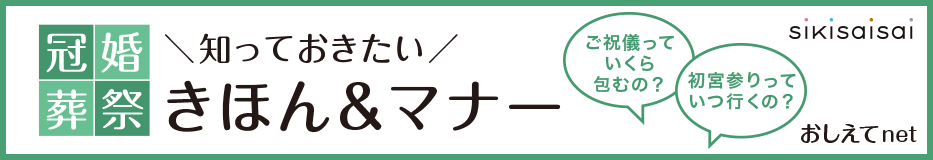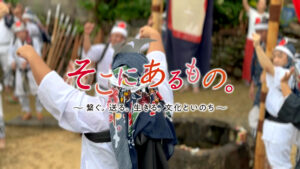【クラス替えや勉強】
新学期、子どもが抱える不安への
寄り添い方
期待と不安が入り混じる新学期。クラス替えや新しい勉強への挑戦は、子どもたちにとって大きな節目です。一方で、環境変化によって不安定な気持ちになりやすい子どももいます。その際、親としてどのように寄り添えば良いのでしょうか?この記事では、長い休み明けで変化の多い新学期に、子どもが安心して学校生活を送れるよう、親が押さえておきたいポイントを解説します。
新学期に注意したい、
子どもの「不安定サイン」

例えば、普段は元気いっぱいなのに急に元気をなくしたり朝起きるのを嫌がったりする場合は、不安定のサインと言えます。また、小学校などの持ち物の準備や着替えが極端に遅くなったり、忘れ物が増えたりする場合も当てはまるでしょう。玄関で毎朝ぐずるなど、学校に行きたがらない場合も、学校で何か心配事や不安を感じている可能性があります。
新学期に子どもが
不安定になりやすい理由
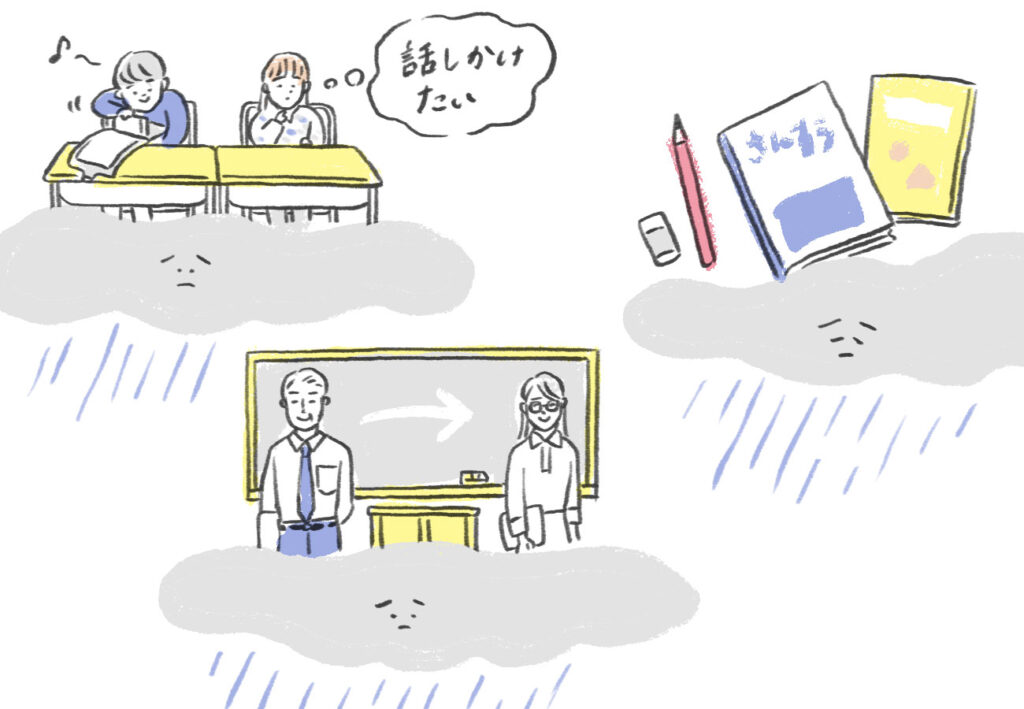
クラス替えがあるから
仲の良い友達と一緒になれるか、新しい友達はできるか、どんな先生が担任か、心を躍らせると同時に不安な気持ちになるのが「クラス替え」です。クラスが分かりそこに馴染むまでは、一人ぼっちにならないかといった不安を感じやすくなる子どもは少なくないでしょう。人見知りだったり、引っ込み思案だったりする子どもにとってはなおさらです。
仲の良い友達と離れてしまった場合、その喪失感の他、新しいクラスで友達ができるか、孤立してしまうのではないか心配になってしまうでしょう。
担任の先生が変わるから
先生が変われば授業の進め方や宿題の出し方など、指導方法も大きく変わることがあり、新しい先生が自分と合うのか不安な気持ちになる子どももいます。人見知りな子どもの場合、新しい先生とのコミュニケーションはハードルの1つとなるでしょう。
勉強が難しくなるから
学年が上がるにつれて勉強の内容が難しくなることは、子どもたちにとって大きな不安の種になります。難しくなった宿題をこなせるか、テストで良い点が取れるかといったプレッシャーを感じるでしょう。中には、周りの子が簡単に理解しているように見えて「自分だけ遅れているのではないか」と焦りを感じる子どももいるかもしれません。
長い休みで生活リズムが
乱れている可能性があるから
長期休暇中は、普段の学校生活と比べて時間に余裕ができて夜更かしや朝寝坊などをして生活がルーズになってしまう子どもも多いでしょう。乱れた生活リズムのまま新学期を迎えると、早起きや授業に集中することが難しくなり、ストレスを感じやすくなります。
親ができる、
子どもの不安を和らげる方法
〜家庭編〜

子どもの心身状態を観察する
子どもの様子をよく観察することから始めましょう。普段と比べて元気がない、イライラしている、落ち着きがない、食欲がないなど、表情や態度の些細な変化がないか観察しましょう。
子どもの声に耳を傾ける
不安そうな様子を感じたら、子どもが安心して話せる雰囲気を作り子どもの心の声に耳を傾けてみましょう。子供と目線を合わせて話を聞いたり、子供がリラックスできる場所で話を聞いたりすることが大切です。「何か困ったことはある?」「学校はどう?」と聞いてみて、子どもが答えてくれたら、「そうか、それは不安だね」「辛かったね」と気持ちに寄り添う言葉を伝えましょう。
安心感を与えるスキンシップを取る
登校前や寝る前に、「行ってらっしゃい」「お休み」などと一声かけてぎゅっとハグをしてあげましょう。温かいスキンシップは子どもに安心感を与え、不安を和らげる効果があります。
勉強を習慣化する
観たいテレビ番組は録画して後刻見るなどの工夫をするなどして、毎日同じ時間、同じ場所で勉強する習慣をつけ、生活リズムの中に自然と学習を取り入れてみましょう。その時、例えば学習時間を記録する表や、できた問題を記録するグラフなどを作って、学習の成果を可視化することで子供のモチベーションアップにつながります。
また、「すごいね」「よく頑張ったね」など、肯定的な言葉をかけて子どものやる気や自信を引き出しましょう。
生活のリズムを整える
生活リズムが乱れてしまった場合、新学期が始まる数日前から少しずつ就寝・起床時間を早め、学校生活のリズムに近づけていきましょう。
学校以外の友達を作る
子どもの興味があるスポーツクラブや習い事をさせるなどをして学校以外のコミュニティを作ってみましょう。学校でうまくいかないことがあっても、別の居場所があることで、気持ちを切り替えやすくなります。
親も一人で抱え込まずに
相談できる人や場所を持つこと
子どもの不安を和らげるためには、親自身が心身ともに健康で余裕を持つことが大切です。そのためには、一人で抱え込まずに相談できる人や場所を持つことが重要になります。親や兄弟、友人やママ友など、心を許せる人に打ち明けてみましょう。もしくは、カウンセラーに相談するのも手です。専門的な知識や経験から、具体的なアドバイスをもらえます。
親ができる、
子どもの不安を和らげる方法
〜学校編〜

不安な場合、担任の先生に相談してみましょう。家庭での様子や気になることを先生に伝えることで、学校での問題や変化に早期に気づき、対応することができます。また、先生間の引き継ぎをお願いすることも有効です。前年度の先生から今年度の先生へ、子どもの情報や注意点などを引き継いでもらうことで、先生は子どもに合った指導がしやすくなります。
しかし、先生も多忙であることを理解し、時間帯や相談時間の長さに配慮し、先生の迷惑とならないように注意しましょう。
不安定な子どもに対して
親がやってはいけないこと
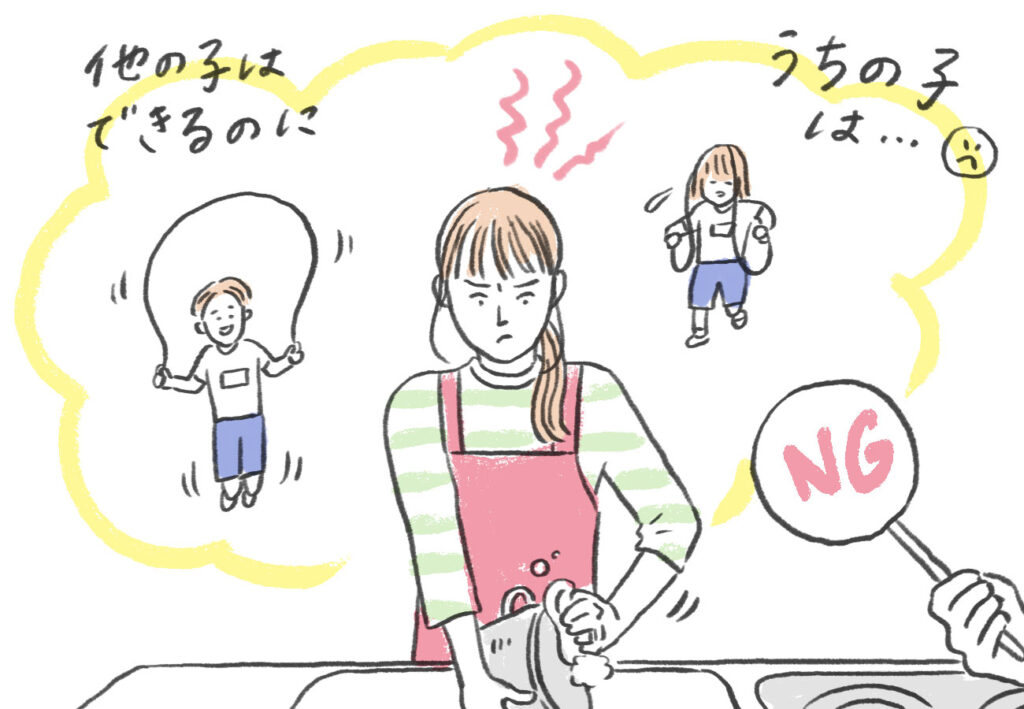
親自身の幼少期と比較すること
自分自身の過去の経験から何かヒントを得ようとするかもしれませんが、自身の幼少期と子どもを単純に比較することはできるだけ避けましょう。時代背景、教育環境、個人の性格など、さまざまな要因が異なるからです。むしろ、「昔はこうだった」「自分はできた」といった無造作な言葉は、子どもに無用のプレッシャーを与えてしまう可能性があります。大切なのは、子どもの個性やペースを尊重し、今の状況に寄り添うことです。
他の子どもと比較すること
「あの子はもう友達ができたのに」「どうしてあなたはまだできないの」といった言葉は、子どもの自己肯定感を低下させます。特に不安定な時期は、周りと比べることで「自分はダメだ」と感じやすいため、注意が必要です。
感情的になって叱ること
お子様の準備が遅かったり、学校に行きたがらなかったりした時、親は焦りや苛立ちを感じてつい叱ってしまうことがあるかもしれません。しかし、感情的になって叱ることは子どもに脅威を与えたり、子どもの不安を増幅させ、状況を悪化させてしまう可能性があります。このような時大切なのは、叱ることではなく、子どもの気持ちに寄り添いじっくりと話を聞いてあげることです。
不安を否定すること
「そんなの気にしすぎだよ」「みんな同じように不安だから」といった言葉は、子どもの気持ちを否定したり軽視するものであり、かえって孤独感を深めてしまいます。子どもの不安を受け止め、「そうだね、不安だね」と共感して寄り添うことが大切です。
まとめ
子どもの中には、新しい環境にゆっくりと慣れていくタイプの子もいます。子どもの個性やペースを尊重して、焦らず見守ることが大切です。この記事でご紹介したポイントを参考に、新しい環境での子どもの成長を温かくサポートしてあげてください。