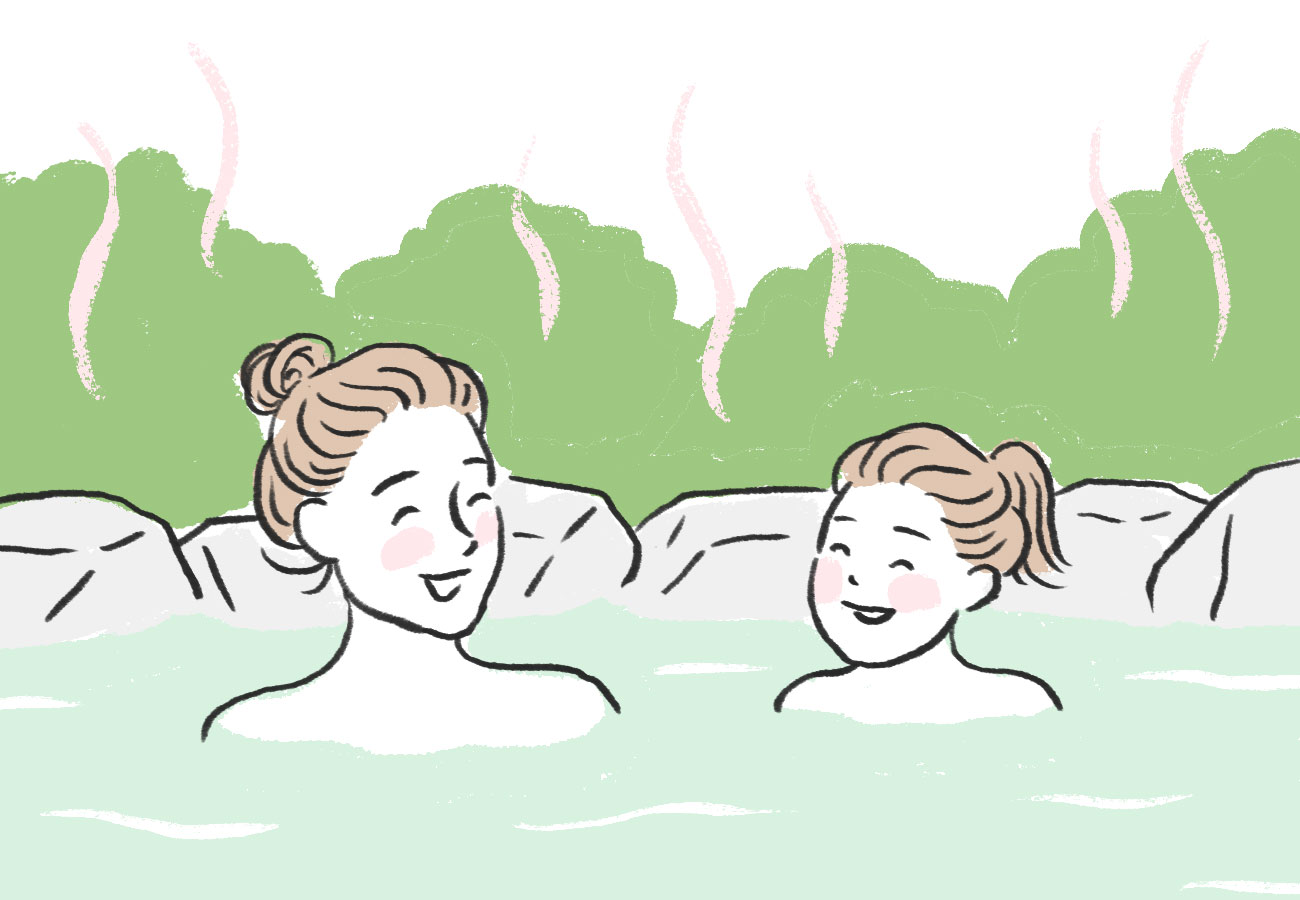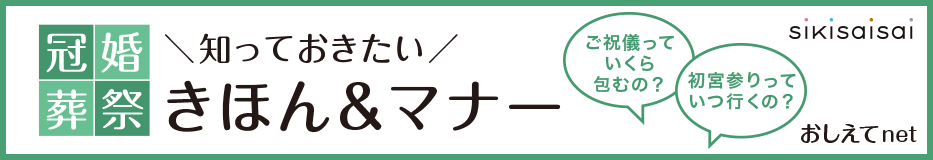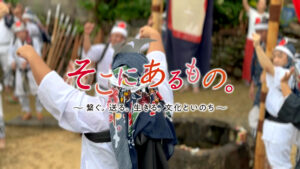連れでも温泉や銭湯を満喫!
親子で守りたい入浴マナーガイド
10月10日は「銭湯の日」です。そして、少しずつ寒くなっていくこれからの季節、お子さんと一緒に温泉や銭湯に出かける計画を立てている方も多いのではないでしょうか。しかし、子連れでの入浴には、大人とはまた違ったマナーや注意点があります。今回は、親子が気持ちよく過ごすために知っておきたい、子連れ入浴のマナーをご紹介します。
子連れでの温泉や銭湯は、何歳からOK?
赤ちゃんと一緒に銭湯を利用できる時期に明確な決まりはありませんが、免疫力が低く湯冷めもしやすいため、生後3ヶ月〜6ヶ月以降を目安にするのが良いでしょう。ただし、大浴場はおむつが外れてからの利用が基本です。おむつが取れていない赤ちゃんの温泉や銭湯の利用は、事前に施設への確認が必要です。また、ベビーバスやベビーチェアが用意されている施設もありますので、調べておくと便利です。
混浴の年齢制限は何歳まで?
異性の子どもと一緒にお風呂に入る場合、年齢制限が設けられている施設がほとんどです。政府の定める目安では、おおむね7歳以上の男女は混浴させないこととされています。施設によってはさらに厳しい年齢制限を設けている場合もあるため、事前に必ず確認しましょう。
温泉・銭湯に行く前に確認したい
ポイントをチェック
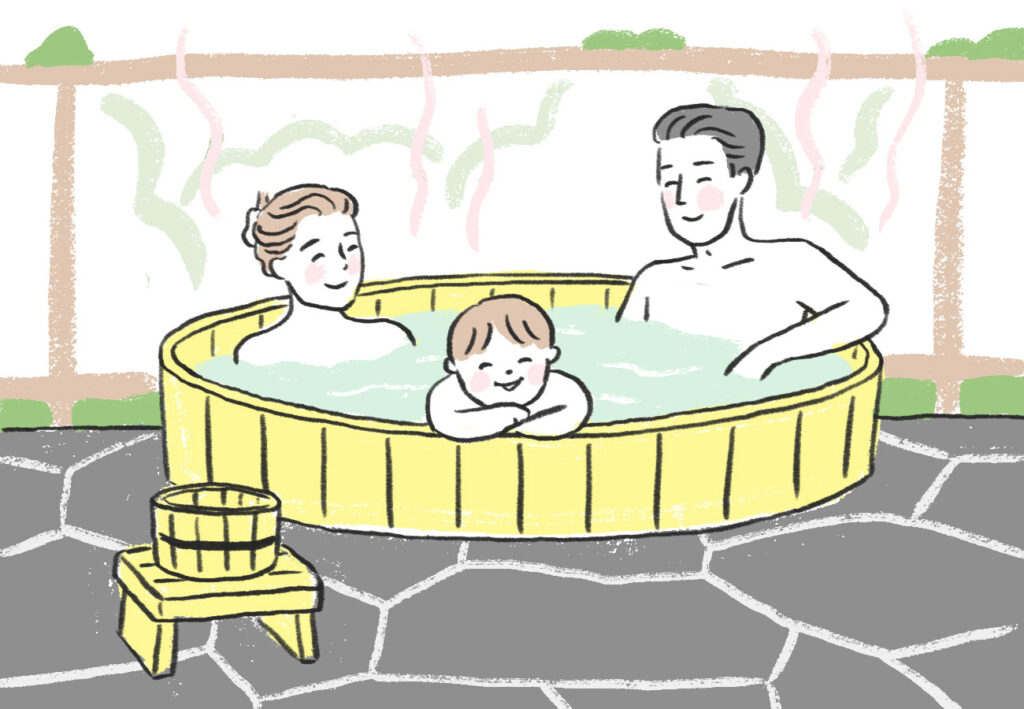
まずは、子連れで温泉や銭湯に行く前に、チェックしておきたいポイントを確認しましょう。
お湯の温度
大人にとっては適温でも、子どもには熱すぎる場合があります。施設によって温度は異なるため、事前にHPなどで確認しておきましょう。複数の湯船がある場合はぬるめのお湯があるかどうかもポイントです。
家族風呂や貸し切り風呂の有無
他の人に気を使わず、家族だけでゆっくりと過ごせる家族風呂や貸し切り風呂のある施設もおすすめです。予約が必要な場合もあるので、早めに調べておきましょう。
宿泊の場合の子どもの年齢制限
温泉旅館などでは、乳幼児の宿泊を受け入れていない場合があるので確認しましょう。
温泉や銭湯に行くときの持ち物は?

基本的なシャンプーやリンス、ボディソープは備え付けがある場合が多いですが、普段使い慣れているものや子ども用のものを持っていくと安心です。
体を拭くためのバスタオルと、湯船に入る前に体を洗うためのフェイスタオルは必須です。子どもは予想外の行動で濡れてしまうことがよくあるので、予備のタオルがあると安心です。また、入浴後すぐに着られるよう、Tシャツやスウェットなど、着替えやすい服を用意しておくとスムーズです。下着も忘れずに準備しましょう。
そのほか、普段使っているベビーローションや保湿クリーム、飲み物、ぐずってしまったときのためのおやつを用意するのも良いでしょう。
入浴前に気をつけたい!
脱衣所と大浴場のマナー

周りの方も気持ちよく過ごせるよう、入浴前に以下のマナーを親子で確認しておきましょう。
脱衣所やお風呂場で
走ったり騒いだりしない
温泉や銭湯での基本マナーです。床が滑りやすく、転倒して怪我をする恐れがある上、他の方の迷惑にもなります。脱衣所やお風呂場では静かに歩くことを教えましょう。
大浴場に行く前に、
子どものトイレを済ませておく
もし、入浴中にトイレに行きたくなった場合は、一度湯船から出て体をしっかりと拭いてからトイレに連れて行きましょう。
シャワーを使う際は、
子どもを椅子に座らせる
シャワーヘッドを動かして使うと、周りの人に水がかかってしまうことが考えられます。子どもを椅子に座らせることで安定して体を洗えます。子どもがシャワーを持つ場合は特にまわりに気をつけましょう。
湯船の中でも注意!入浴中のルール

湯船に入る際や、入浴中もマナーを守ることが大切です。
泳がない
温泉や銭湯の基本マナーの1つです。湯船はプールではないので、泳いだり潜ったりしないようにしましょう。
体を洗ってから湯船に入る
湯船はみんなで使う場所です。石鹸で体を洗い、きれいに流してから入りましょう。
長い髪はゴムなどでまとめる
髪の毛がお湯の中に入らないように、長い髪はまとめてから湯船に入りましょう。
かけ湯をする
湯船に入る前に、手桶を使ってお湯を体にかける「かけ湯」をしましょう。急な温度の変化に体がびっくりしないように、心臓から遠い足元からゆっくりとかけてください。
子どもから目を離さない
子どもは湯船で転んだり、溺れたりする可能性があります。絶対に目を離さないようにしてください。
熱すぎないか確認し、長湯にも気をつける
大人には適温でも、子どもには熱い場合があります。また、子どもはのぼせやすいので、長湯は避けて適度な時間で上がるようにしましょう。
まとめ
子連れでの温泉や銭湯は、大人だけの利用とは違った配慮が求められます。しかし、事前の準備やマナーを親子で確認することで、子どもにとっては社会のルールを学ぶ貴重な体験となるでしょう。親子で心身ともにリフレッシュして、楽しい時間を過ごしてください。