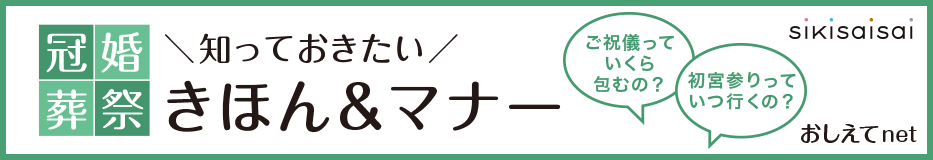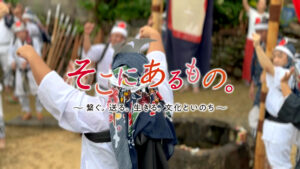【ご先祖様を迎える前に知っておきたい】
お盆にやってはいけないタブー6選
お盆は、ご先祖様の霊をお迎えし、感謝の気持ちを伝えて供養する大切な期間です。実は、昔からこの時期には「やってはいけない」とされることがいくつかあるのを知っていますか?今回は、そもそもお盆がどのような行事なのか、そしてお盆に避けるべきと言われている慣習について詳しくご紹介します。
そもそもお盆とは?

お盆は、ご先祖様の霊を供養する仏教行事です。地域によっても異なりますが、一般的には迎え盆の8月13日から16日の送り火までの4日間を指し、この期間にご先祖様の霊が子孫の元へ帰ってくると考えられています。
この時期には、ご先祖様の霊を迎え、供養するためのさまざまな慣習があります。具体的には、お墓参りをしてご先祖様にご挨拶をしたり、仏壇の前にキュウリの馬やナスの牛を飾った精霊棚を設けてお供えをしたりします。また、ご先祖様の霊をお迎えし、お送りするための迎え火・送り火を焚いたりもします。
また、お盆は親族が集まる貴重な機会でもあります。普段なかなか会えない家族や親戚が一堂に集まり過ごすことで、家族の絆を深めることができる大切な時でもあります。
お盆にやってはいけないこと
1. 川や海などの水辺に近づくこと

お盆の時期は、あの世とこの世の境目が曖昧になり、水辺は霊の通り道になると考えられています。水辺で遊んでいると亡くなった人の霊に足を引っ張られる、連れていかれる、などの言い伝えもあります。
水難事故に遭いやすい時期であることや、お盆を過ぎるとクラゲが増えるといった現実的な危険もあり、近づくのは控えましょう。
2.生き物の命を粗末にすること
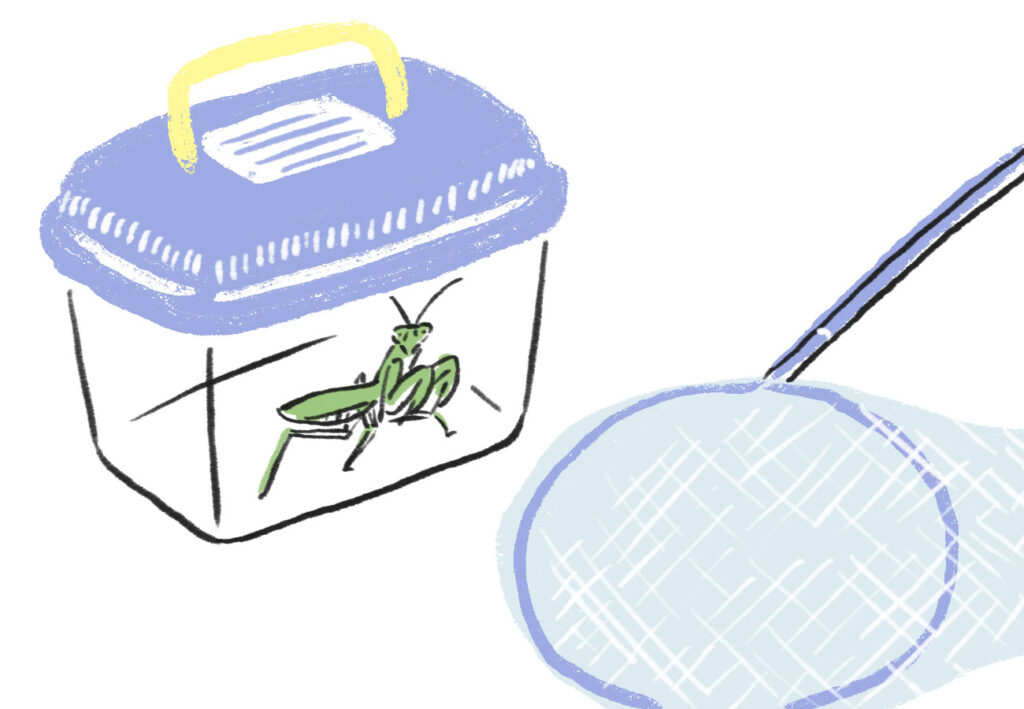
仏教では「不殺生(ふせっしょう)」という教えがあり、生き物を殺してはいけません。お盆は特にこの教えを重んじる期間です。また、ご先祖様の霊が蝶やトンボなどの虫に乗って帰ってくるとも言われており、むやみに生き物を殺すべきではないとされています。釣り、虫取りなども避けるのが無難です。
一方で、お盆期間中に肉や魚を食べる行為自体は問題ないとされています。ただし、必要以上にたくさん食べる行為は控えましょう。
3.お祝い事や派手な遊び

お盆はご先祖様を供養し、静かに過ごす期間です。そのため、入籍、結婚式、新築祝いなどの慶事や、海水浴、キャンプ、バーベキューといった賑やかなレジャーは控えたほうがよいとされています。ご先祖様を放っておいて楽しんでいる印象を与える、という考え方もあります。
4.針仕事

針仕事をしていると、うっかり指を刺して血が出てしまう可能性があります。仏教では「血」を「けがれ」と捉えるため、お盆に血を流す可能性のある行為は避けるべきとされています。
5.トゲや毒のある花などを飾る
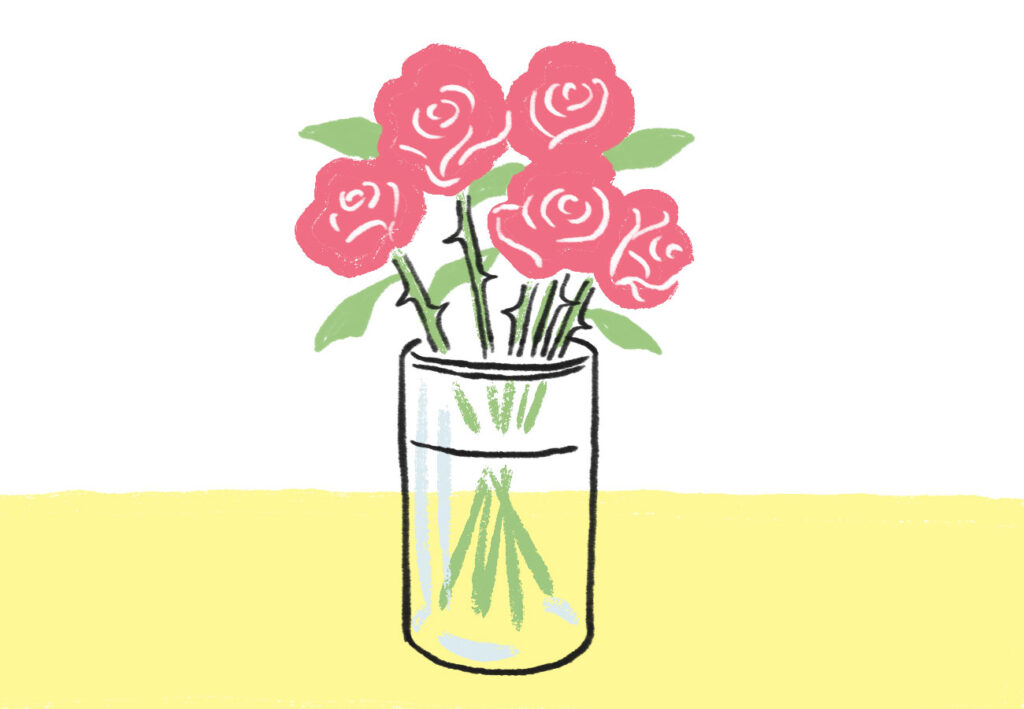
バラなどトゲのある花を飾ることも、針仕事と同様の理由で避けるべきとされています。毒性のある花も飾るのをやめましょう。「毒を盛る」と捉えられることがあります。また、花がまるごと落ちる椿の花・日持ちがしないダリアやガーベラなどの花は死を連想させるので飾るのは控える方が良いとされています。
6. 納車

ご先祖様をお迎えしている大切な時期に、大きな買い物をしたり、新しいもので浮かれたりするのは、ご先祖様に対して失礼にあたるという考え方があります。お祝い事と見なされる側面もあるため、避けるのが無難です。
まとめ
現代では、お盆にまつわる慣習を昔ほど厳しく守るよう求めたりすることは少なくなりました。しかし、これらの言い伝えの背景には、先祖供養を行うお盆という期間を大切にしようという深い思いが込められています。こうした豆知識を知っておくことで、より丁寧かつ穏やかな気持ちでお盆を過ごし、ご先祖様への感謝を深めることができるでしょう。