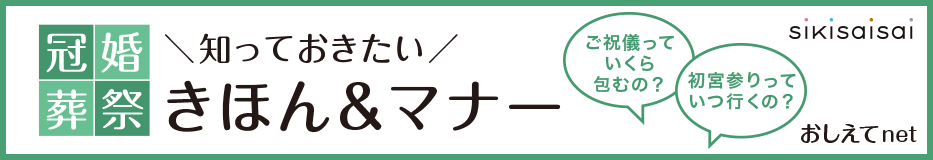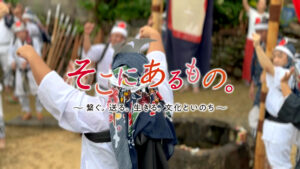【うなぎを食べるのはなぜ?2025年はいつ?】
土用の丑の日のキホン
「夏バテ防止にうなぎ!」でお馴染みの土用の丑の日。でも、「そもそも土用って何?」「なぜうなぎなの?」と聞かれると、意外と答えられない方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、知っているようで知らない土用の丑の日のキホンを紹介します。
「土用」とは? 実は年に4回ある!

土用と聞くと夏を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、実は立春、立夏、立秋、立冬の直前の約18日間を指す期間で、年に4回あります。このうち特に立秋前の夏の土用は「小暑」から「大暑」のころにあたり、夏の気のもっとも盛んなときであることから、一般的に強く認識されています。なお、この夏の土用の期間を「暑中」ともいい、この期間に出すのが暑中見舞です。その後の立秋を過ぎると残暑見舞となります。
そもそも土用は、中国から伝わった陰陽五行説に関係しています。古代中国の陰陽五行説では、万物は「木・火・土・金・水」の5つの要素で成り立つと考えられていました。春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」と季節を割り当てました。そして、各季節の終わりの約18日間に「土」を割り当て、これを「土用」と呼ぶようになったともいわれています。
2025年(令和7年)の「土用の丑の日」は以下の日にちです。
冬…1月20日(月)、2月1日(土)
春…4月26日(土)
夏…7月19日(土)、7月31日(木)
秋…10月23日(木)、11月4日(火)
「丑の日」とは?
旧暦では、日を十二支(子・丑・寅…)で数えていました。「丑の日」とは、12日ごとに巡ってくる丑の日にあたります。したがって、「土用の丑の日」とは、「土用の期間中にある丑の日」ということになります。土用の期間は約18日間あるため、年によっては丑の日が2回巡ってくることもあり、その場合、1回目を「一の丑」、2回目を「二の丑」と呼びます。
ちなみに、2025年の夏の土用の丑の日は2回あり、一の丑は7月19日(土)、二の丑は7月31日(木)になります。
どうして「うなぎ」を食べるのが定番に?

うなぎは滋養強壮に良いというのは万葉集にも出て来るところですが、夏の土用の丑の日にうなぎを食べる風習が定着したのは、江戸時代からと言われています。これにはいろいろな説がありますが、最も有名なのが発明家・平賀源内が考えたという説です。
夏になるとうなぎの売れ行きが落ちて困っていたうなぎ屋から相談を受けた平賀源内が、「本日、土用の丑の日」という張り紙を出すことを提案。すると、これが大当たりして他のうなぎ屋も真似するようになり、夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣が広まったと言われています。
また、うなぎにはビタミンAやB群など、夏バテ防止や疲労回復に効果的な栄養素が豊富に含まれており、理にかなった習慣とも言えるでしょう。
うなぎだけじゃない!土用の日の縁起物
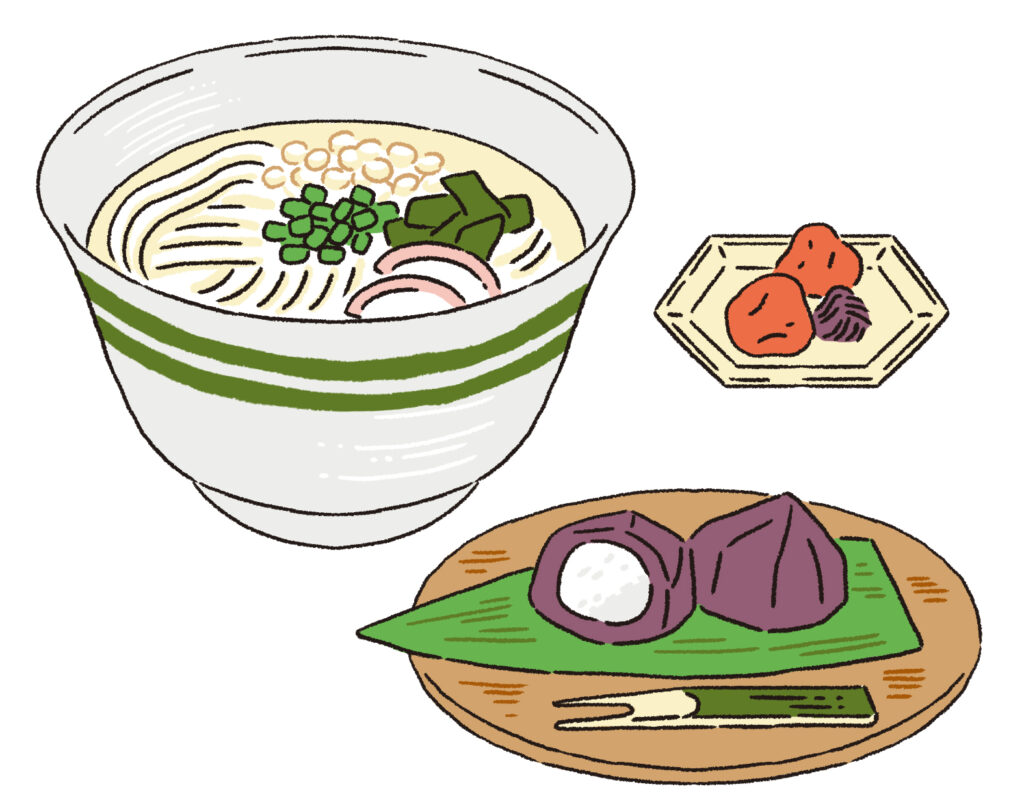
土用の丑の日に食べると良いとされるものは、実はうなぎだけではありません。
「う」の付く食べ物
梅干し、瓜(うり、きゅうり、すいか等)、うどんなど、丑の日にちなんで、「う」の付くものを食べると夏負けしないという言い伝えがあります。
土用しじみ
「土用しじみは腹薬」ということわざがあるように、この時期のしじみは栄養価が高く、特に肝臓の働きを助けるため、夏バテに良いとされています。
土用餅(土用おはぎ)
あんころ餅のことを言います。小豆の赤色は厄除けの意味があり、土用の期間に食べることで無病息災を願いました。
お灸
昔からお灸を据えて夏を乗り切るならいもあります。
まとめ
今年の夏の土曜の丑の日は2回。あるので、うなぎを食べるのはもちろん、「う」の付く食べ物などを食卓にうまく取り入れて、楽しみつつ有意義に過ごしてみてはいかがでしょうか。そして、暑い夏を元気に乗り切りましょう。