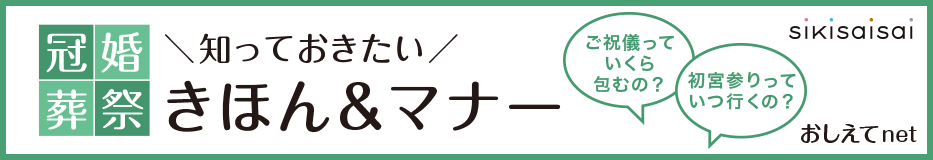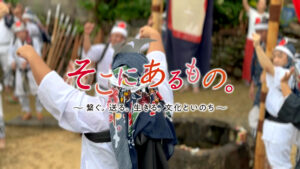【実りに感謝する行事】
新嘗祭って知ってる?
秋になると各地で収穫祭が行われますが、その中でも日本の伝統として古くから大切にされてきた行事が、毎年11月23日に宮中や全国の神社で行われている「新嘗祭(にいなめさい)」です。実は、私たちが祝日として過ごしている「勤労感謝の日」のルーツでもあります。今回は新嘗祭について、由来や風習、取り入れ方をご紹介します。
新嘗祭とは?
新嘗祭(にいなめさい)は、別名「しんじょうさい」とも呼ばれ、その年の収穫に感謝し、翌年の豊作を祈願する重要な祭祀です。
その歴史は非常に古く、奈良時代に完成した『日本書紀』にも、「新嘗」の言葉が使われるなど、収穫に感謝する儀礼が昔から続いているといわれています。
特に、天皇が即位して初めて迎える年に行われる「大嘗祭(だいじょうさい)」は、皇室における最も重要な祭祀のひとつ。かつては宮中でのみ、新米を神に供え、その年の収穫に感謝する儀式が行われていましたが、次第に全国の神社でも神事として広まりました。
戦後、この日が国民の祝日「勤労感謝の日」と定められたことで、新嘗祭は私たちの暮らしにもより身近な存在となりました。かつての日本は農業が生活の中心でしたが、近代化や都市の発展により暮らしのあり方が変化したことから、「豊作を含むすべての仕事に感謝を捧げる日」としての意味合いも込められています。
何をするの?
宮中で行われること

新嘗祭は、皇居内にある宮中三殿に附属する「神嘉殿(しんかでん)」という建物で行われます。前日には魂を鎮めるための「鎮魂の儀」が執り行われ、当日には「夕の儀」、さらに翌24日の未明にかけて「暁の儀」が続きます。天皇陛下がその年に収穫された新穀を神に供え、自らも口にされるという、厳粛な雰囲気の中で行われる大切な儀式です。
神社で行われること

全国の多くの神社でも、同じ日に新嘗祭が行われます。近隣の人を招いてお供物を分けたり、舞の奉納やその他のイベントが開催されたりする神社もあります。
新嘗祭を楽しんでみよう

新嘗祭は特別な行事ですが、家庭でも気軽に取り入れられます
- 新米を炊いて食べる
秋の実りを家族で味わい、自然の恵みに感謝しましょう。子どもやパートナーと一緒におにぎりを握るのも楽しい体験に。 - 神社のお祭りに参加してみる
新嘗祭を行っている地域の神社へ行ってお参りするだけでも、実りの大事さやありがたみを実感できるきっかけに。 - 子どもと「いただきます」の意味を話してみる
農家さんや自然へのありがとうを伝えたり、「いただきます」というあいさつの意味を話し合ってみたりなど、親子で食べ物に感謝する時間を作ってみましょう。
まとめ
新嘗祭は、古代から続く「実りに感謝する日本の伝統行事」。毎年11月23日は、勤労感謝の日として過ごすと同時に、家族で新米を味わったり、食べ物に感謝の言葉を交わしたりする日にしてみませんか。